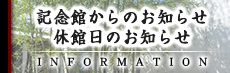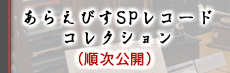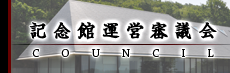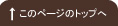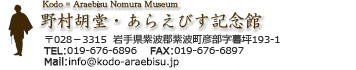作成者別アーカイブ: kodo-admin
野村館長のつぶやき…
館長がせっせとお世話をしていたウチワサボテンが、 かわいらしい花を咲かせました!! =*= ウチワサボテン =*= 先端のトゲは、まだやわらかい~ またお花の話題か!……と思わないでくださいね(笑) このウチワサボテンは、 野村館長が、藤倉四郎さん(童話作家で、胡堂と深い交流があった)と一緒に 胡堂ゆかりの日本画家を訪ねるため、 神奈川県の葉山へ出かけた際に手に入れたそう。 おじさんが仕事をしていた伊東にも、同じサボテンがあったなぁ と、野村館長のつぶやきが…。 胡堂は、静岡県の伊東にある別荘で 『銭形平次捕物控』を執筆していました。 そして、館長からすると野村胡堂は“親戚のおじさん”なんですね。 (野村館長は、胡堂の弟・耕次郎の孫なのです!) サボテンの花をきっかけに、館長に野村胡堂の思い出を聞いてみました。 以下、館長のおはなし。 おじさんの仕事場は伊東の駅から近い。 駅前に大きなきなウチワサボテンがあったのを覚えている。 葉山で同じサボテンを見つけ、このことを思い出して買ってきた。 おじさんに逢いに行ったときのこと。 土産に持っていった豆銀糖(まめぎんとう)を喜んで食べてくれた。 東京暮らしは長いが、紫波に帰って来たときは紫波訛りで話をする。 全く気取らない、普通の親戚のおじさんとおばさんだったなぁ…。 『銭形平次捕物控』の連載を27年間も続け、作品数は383編。 そのほかに音楽評論も書き、野村学芸財団を設立し、 紫波町の“名誉町民第一号”になった野村胡堂ですが、 館長曰く、「普通のお父さんであり、伯父さん」だったようです。 好きなものは濃いお茶。 甘いものもよく食べる。 … 続きを読む
記念館は花ざかり~*
岩手県内の桜も満開を過ぎ、そろそろ葉桜になってきたそうですね。 しかし当館の桜は、まさに今、見ごろをむかえています~!!(*^ ^*) 「桜、なかなか咲かないなぁ…。まさか、鳥に食べられたわけじゃないよね…?」 と言って噂をしていると、焦ったように一気に咲くのが、当館の桜たち(笑) 隣の小学校の桜と比べても、約10日くらい開花の時期が遅い。 焦っているわけでなく、そういう品種なのです。(のんびり屋の桜…?) 今日は 天気が良かったので、 満開の桜 と記念館を囲む花の写真をたくさん撮りました~(^^)! =*= サクラ&記念館 =*= (( 記念館の大駐車場 )) ちょっと変わった角度? 桜の木の下から記念館を撮りました。 =*= サクラ&東根山 =*= 右側にぼんやり写っている、台形の山が「東根山(あずまねさん)」です。 こたつの形に似ているので、「こたつやま」とも呼ばれているんです♪ =*= サクラ&ハナミズキ =*= 奥の白い花がサクラ、手前のピンク色の花がハナミズキです。 青空にぐんぐん伸びています! 5月になると、この木の下にラベンダーが咲きます。楽しみだなぁ♪ =*= 菜の花と記念館 =*= (( 記念館の大駐車場 )) 記念館とサクラと菜の花のコラボレーションを実現しようと、 菜の花畑の中から撮りました。 気付いたら… 「スカート黄色いぞ!」 …花粉だらけになっていました。 菜の花畑はこんなに広いですよ!456号線からも見えるはずっ♪ 幼稚園児の頭の高さくらいありますよー! … 続きを読む
福山雅治さんが歌う!「銭形平次」(CDアルバム「魂リク」)
4月8日(水)に発売され、いま話題の 福山雅治さんのカヴァーアルバム 「魂リク」 このアルバムの第1曲目に 「銭形平次」 が収録されています! そして! 4月14日(火)発売のサンデー毎日に、この話題に合わせて、 野村胡堂・あらえびす記念館の紹介が掲載されました! ありがとうございます m(_ _)m 福山さんのCDアルバムが、テレビなどで紹介された日は、 記念館職員のあいだでも、とても話題になったんです(^^) もちろんCDもゲットして、みんなで聴かせていただきました~♪ いや~、福山さんの銭形平次、シビレますねぇ~~~ 本当に素敵で沁みる歌声でうたってくださり大大大感激!!! とても嬉しいです(^^)★ 当館自慢の音響設備をそなえたホールで、 館長と、福山さんの「銭形平次」を聴きながら、 「いつか福山さんに、記念館ホールで銭形平次の弾き語りをしてもらいたいですね~・・・」 「んだんだ!来てくれたら、こんなに嬉しいことはないなぁ~・・・」 と、盛り上がっています! (「んだんだ!」←岩手の方言で「そうだね!」という、同意の意味。) ちなみに当館は、、、 これまでに、たくさんの著名な方が来館しているんですよ! ○指揮者の小澤征爾さん ○チェリストのロストロポーヴィチさん ○作家の林望さん ○作家の高橋克彦さん(岩手出身) ○脚本家の内館牧子さん ○ジャズピアニストの秋吉敏子さん ○演出家の實相寺昭雄さん ○女優の原知佐子さん そして、テレビドラマなどで銭形平次を演じられた ○俳優の北大路欣也さん ○村上弘明さん(岩手出身) ○お笑い芸人のハイキングウォーキング鈴木Q太郎さん … 続きを読む
太田代政男先生、4年間ありがとうございました!!
平成23年からあらえびすレコード定期コンサートの 解説員として携わっていただいた太田代政男先生が、 今年度3月の開催をもちまして、解説員を退任されました。 あらえびす(野村胡堂)が収集したSPレコードとその評論を クラシック初心者にも親しみやすいように、 ご自身の音楽経験をふまえながら解説してくださいました。 そして、時には、、、 素晴らしい歌声を披露してくださるなどのサプライズ(!!!)もあり、 太田代先生のレコードコンサートはとても楽しい時間でした(^^)♪ 約4年間という長い間、大変お世話になりました。 太田代政男先生、本当にありがとうございました! (こちらの2枚の写真は参加者の方の提供。ありがとうございます。) さて!!! あらえびすレコード定期コンサート、4月からの新しい解説員は、、、 音楽学研究家で美術史にも詳しい フランコ・マウリッリさん(イタリア・ローマ出身) です。 何度かレコードコンサートを開催したことがあるので、ご存知の方もいるのでは・・・? あらえびすレコード定期コンサートは、(変更する場合があるかもしれませんが!!) 偶数月を侘美淳先生、奇数月をフランコ先生に担当していただきます。 どんなお話をしてくださるのか…、楽しみですねっ♪” 詳しい日程などは、【イベント情報】 または 【直接記念館に】 お問合せください。 4月からもご来場お待ちしております! 2015.3.15 sakuyama
絵美夏アルパコンサート★レポート
2月14日(土)バレンタインの日に、 絵美夏アルパコンサート~ハープと歌で贈る 優しく美しい あなたへのメロディー~ を開催しました!!!! 前日まで雪が降ったりやんだり…で、道路状況を心配していましたが、 コンサート当日はすかっり晴れたいいお天気!! (コンサートホールはちょっと暑いくらいでしたね、すみません(^^;)) 今回演奏してくださったのは、紫波町出身のアルパ奏者、絵美夏さんです♪ ところで「アルパ」とは・・・? スペイン語で「ハープ」のことで、英語で「インディアン・ハープ」とも呼ばれるそう。 その昔、スペイン人によって南米に持ち込まれ、発展していったのが「アルパ」です。 メキシコ、ヴェネズエラ、パラグアイなどインディオ系の民族楽器の一種です。 (新音楽辞典/音楽之友社による) 今回は、3台のハープを使い分けて演奏してくださいました☆ オーケストラのハープ(「グランドハープ」と言われます)より小さく、重さ5~7キロ程度。 楽器の中が空洞なので、大きさのわりに軽いんですね! (我が家の猫と同じ重さでびっくりです。あれ?うちの猫ちょっとメタボかしら…?笑) 右肩に傾けて演奏し、グランドハープのような足元のペダルはありません。 両手で弦をはじいて音を出すので、音色は日本の琴にとても似ています♪ でも、琴のように演奏するための「爪」はありませんので、 琴よりもポ~~~ンと響く感じですね♪ 素朴で優しい音色とラテンの華やかなリズムがとても良かったです! あまり目にしない楽器なので、、、というより、 たぶん初めて見る方がほとんどだったと思いますが、 来場者はステージを覗き込みながら聴き入っていました。 プログラムは、 ♪シエリトリンド ♪モリエンドカフェ(コーヒールンバ) ♪ルナジェナ ♪アルパの祈り … 続きを読む
ナイトミュージアム~あらえびす記念館で月の観察会~★レポート
企画展『胡堂が夢見た月世界~太郎の旅 月世界のたんけん~』の開催期間中に、 月世界にちなんで★ナイトミュージアム あらえびす記念館で月の観察会★を開催しました! 第1回は月のクレーターを、第2回は月の模様を観察しました。 残念ながら、第2回は天候が悪く、月に雲がかかっていたため、 月を見る事ができません・・・・・・と、思いきやーーー!! 観察会終了後にやっと月が見えて、観察することができたんです! 寒い中、月が出るまで粘り強く待った甲斐がありました~… ★ ティコクレーター ★ クレーターの○の中の、小さな山(「中央丘」と呼ばれています)も発見~! ★ スバル ★ 肉眼で、7つの明るい星を数えることができました! この月と星の写真(↑)、実は私のスマートフォンで撮影したものなんです! 意外とキレイに撮れちゃうんですね~♪ しっかりクレーターが写っていて、我ながら上手く撮れたなぁと(^皿^*)笑 クレーターや模様を、自分の眼で見ることができただけでも感動しましたが、 講師の先生に、月の模様や星座について教えてもらい、 空を見上げるのが好きになりました(^^) 今の季節は少し寒いけれど、たまには電気を消して、 夜空を見上げてみるのもオススメです☆ ナイトミュージアムに参加してくださった皆さん、ありがとうございました! 胡堂も、こんなふうに月をながめて小説を書いたのかなぁ~…… 2014.2.6 sakuyama
企画展「胡堂が夢見た月世界」~3月15日まで開催中!
久しぶりのブログ更新!(^^; すごーーーくお待たせしてしまいましたが、 今日は、現在開催中の企画展について紹介したいと思います。 今年度の企画展では、 「胡堂の代表作『銭形平次捕物控』以外の作品も紹介しよう!」と思い、 前期は、歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に影響を受け執筆した 時代小説『三万両五十三次』 そして後期は、胡堂が子ども達に向けて執筆した 科学と夢の小説『太郎の旅 月世界のたんけん』を取り上げ、 現在、企画展『胡堂が夢見た月世界~太郎の旅 月世界のたんけん~』を開催しています。 『太郎の旅 月世界たんけん』という小説は、 野村胡堂が執筆した子ども向け小説の第1作目です。 大正14(1925)年に、胡堂が勤めていた報知新聞社の連載小説として発表され、 翌年の大正15(1926)年、単行本として子供の科学社から出版されました。 ちなみに・・・ 『銭形平次捕物控』は昭和6年(1931年)に発表されたので、 『太郎の旅 月世界のたんけん』は、銭形平次よりも前に発表された作品です。 胡堂が執筆した小説(音楽評論は含まない)は、全部で684作品! その中で子ども向けの小説を37作品書いています。 半分以上が『銭形平次捕物控』なので、 子ども向け作品は、全体のたったの約5%しかありません。 しかし、そのひとつひとつが、子どもたちがワクワクするような作品ばかりなんです! 明治から昭和にかけて、国内外問わず、多くの作家が科学小説を執筆してきましたが、 『太郎の旅 月世界のたんけん』は科学とファンタジーを交えた作品で、 今回の企画展では、「科学」の部分に焦点をあてて紹介しています。 (出来ることなら、ストーリーもまるごと紹介したかった~!!!) 小説の登場人物の太郎と花子が、科学者の伯父さんと月を旅するという内容。 胡堂は、登場人物の会話の中で、たくさんの科学の知識を散りばめています。 例えば・・・ 月までの距離は…? 月の一日の長さは…? 光の速さは…? どうして月はうさぎの模様になっている…? 大人でも「あれ?どうしてだろう?」と、興味をそそられるような内容ばかり! 胡堂が巻頭で「決してでたらめは書かなかった」と言っているように、 … 続きを読む
あらえびす記念館から見る夕日写真コンテスト!
記念館ギャラリーでは、彦部公民館主催の 「あらえびす記念館 夕日写真コンテスト」の作品を10月31日まで展示しています♪ タイトル通り、野村胡堂・あらえびす記念館から見た夕日の写真を、 地元の彦部公民館写真部や一般の参加者から募集し、コンテストを行ったものです。 作品は全部で19点!いろいろな夕日の姿が楽しめます♪ このコンテストでは、一般の来館者による投票と、 写真部講師、彦部公民館長、当館の館長に投票をお願いし、賞が決定します。 賞は 【最優秀賞】 【優秀賞】 【野村胡堂・あらえびす記念館館長賞】 の3つで、 10月21日にその結果が発表されました!! では、入賞作品をご紹介~~~♪ 最優秀賞 : (タイトル無し) 佐藤まゆみさん 記念館芝生から夕日を撮る方が多い中、胡堂の歌碑がある駐車場付近から撮影しています。 夕日とコスモスと、うっすら残る青色のコントラストが美しいという評価でした。 コスモスが秋の雰囲気を出している素敵な写真だなーと思います★ 優秀賞 : 「夕日のガラスの鏡」 阿部アツ子さん カメラを夕日に向けるのではなく、夕日を写した記念館の窓に向けて撮影した、ユニークな作品。 窓には、東根山や雲の形までくっきりと写しだされています。 記念館の素敵なワンシーンを撮っていただき、嬉しいです! 彦部公民館長の阿部館長さんより、表彰状が授与されました。 おめでとうございます(*^○^*) 野村胡堂・あらえびす記念館館長賞 : 「夕日の輝き」 鷹觜汎使(ひろし)さん 夕日をさえぎる黒く厚い雲の隙間から、力強い光が差し込んでいる様子。 厚い雲があれば「今日は夕日が見えないな…」なんて思ってしまいますが、 粘り強くシャッターチャンスを待ったのでしょう…。 幻想的な夕日の姿だなぁと思いました★ 入賞の3作品以外も、素敵な写真ばかりですよ(^^)♪ あと、タイトルもおもしろいんです!! 「こうだったら今頃ジャニーズ」とか、「明日もいいことありますように!」とか… 次回はぜひ【ユーモア賞】を作っていただきたい!!! 写真展は10月31日まで!!19点の作品を展示しています。 … 続きを読む
キッズフェスティバルinあらえびす2014★レポート④~夜の観察会編~
キッズフェスティバルinあらえびす2014最後のレポートになりました。 昨年から実施している夜の部では、星空と昆虫の観察会です。 昼は晴れていたのに、夕方から徐々に雲行きが怪しく……午後6時過ぎると大雨!!! 昆虫観察はいったん中止し、場所を軒下に変更して再スタートしました。 「ライトトラップ」とう方法で、茂み向かって光を発し、集まってきた昆虫を観察しました。 大きな蛾や虫はなかなか見られませんでしたが、小さな虫たちは集まってきた様子。 子どもたちは、自分の昆虫図鑑やルーペを持って、一生懸命観察していました。 お家で育てている昆虫を、持ってきてくれた子もいましたね! 講師の先生方も(子ども以上に!?)はりきって観察していました。 狭いスペースでしたが、和気あいあいとした雰囲気で、 雨なんかへっちゃら!というくらい、楽しんでいたようです♪ 星空観察も、雲が厚かった&雨ふりだったので、 観察が難しく、ホールで映像による星のお話やミニプラネタリウムを体験しました。 盛岡市子ども科学館の武田さん高橋さん(タカタケコンビ)のお二人のお話は、 とても分かりやすく、クイズ大会もあり、楽しく星について学ぶことができました!! ちなみに…… 「星」と「虫」には共通点があるんです!! 「ヘラクレスオオカブト」や「ケンタウルスオオカブト」というカブトムシの名前、 聞いたことありませんか(^^)? 実は、星にも「ヘラクレス」や「ケンタウルス」という星座があるそうです! 意外な共通点に、大人もなるほど~の声でした! 「星」と「虫」の体験コーナーを行ったり来たりして、 子どもたちは楽しみながら学べたようです(^-^)♪ 以上、4つに分けてキッズフェスティバルinあらえびす2014の様子をご紹介しました。 最後になりましたが、ご協力くださいました各団体、講師の皆様、ボランティアの中学生の皆さん、 大変ありがとうございました☆ 来年は、夜も晴れますように!!! 2014.9.18 sakuyama
キッズフェスティバルinあらえびす2014★レポート③~和の心体験編~
キッズフェスティバルinあらえびす2014のレポート3つ目は、 館内で行った、和の心を体験するコーナーの紹介です! ギャラリーではお煎茶の作法を体験、ホールでは琴や尺八に触れる体験です。 外の芝生を眺めながら、ゆったりとした気持でお煎茶の体験ができました。 こちらはお琴体験。おかさんも一生懸命!! この体験で、「さくらさくら」が弾けるようになるんです! 子どもたちも琴の音色にハマってしまうようで、なかなか琴から離れられません(o^皿^) こちら(↑)は、尺八の体験!なかなか触れることができない楽器ですが、 吹きやすいように工夫したり、丁寧に指導してくださるので、楽しく体験できました♪ ちょっと吹いて聴かせて、とお願いすると、元気にピー!!!と披露してくれました(^^) お琴と尺八を指導してくださった、紫水会と竹風会のみなさんは、 近々演奏会があるそうですので、どうぞ足をお運びください♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 稱名寺観月会 (しょうみょうじ かんげつかい)~お寺の小さなコンサート~ 平成26年9月23日(火)午後6時30分~ 入場無料 会場 稱名寺本堂(紫波町片寄字鶉森6-3) プログラム ♪春の海(宮城道雄作曲) ♪さくらさくら・うさぎ(日本古謡) ♪ハナミズキ(マシコタツロウ作曲) ほか ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ レポート~夜の観察会編~に続く 2014.9.18 sakuyama
キッズフェスティバルinあらえびす2014★レポート②~芝生広場編~
キッズフェスティバルinあらえびす2014のレポート2つ目は、 芝生広場での昔あそび体験を、写真たっぷりでご紹介します! 芝生広場では、昔あそびの体験コーナーがあります。 わなげ、竹馬、メンコ、紙ヒコーキ、水でっぽう、フラフープ、弓矢…… 子どもたちにとってはちょっと新鮮な、大人にとっては懐かし遊びを、親子で楽しんでいるようでした。 こちら(↑)は、メンコで遊んでいる様子。 丸く切った厚紙を、何枚か重ねて厚さを出し、両面に絵を書いてオリジナルめんこの出来あがり!! 毎年好評の、餅つき体験もやりました! 子ども用の小さいきねを使い、「よいしょ~!」という掛け声に合わせてぺったんぺったん!! ついたお餅は、その場でいただきました!やわらかくって、美味しいっ☆ ごま&おしょうゆ、きなこの味は、地元のおかあさんの味ですね~♪ イベントの途中で、地元大巻まつりの山車が到着し、ますます華やかになりました☆ 地域の青年会、婦人会による手作りの山車は、迫力満点です!! 音頭上げと威勢の良い掛け声、子どもたちによる元気な太鼓で、記念館を出発して行きました。 お天気にも恵まれ、大盛り上がりの芝生広場なのでした~! レポート~館内・和の心体験編~に続く 2014.9.18 sakuyama
キッズフェスティバルinあらえびす2014★レポート①~舞台発表編~
今年で9回目を迎えた、キッズフェスティバルinあらえびす!! お陰さまで今年も大盛況でした! 今日は、キッズの様子を、写真たっぷりでご紹介します~(^O^)♪ 子どもたちが主役の舞台発表! 一つ目の団体は、紫波町山屋地区に伝わる「山屋田植え踊り」です♪ その昔、紫波町山屋地区では砂金がよく取れ、砂金堀りの支配人として京より往来した「孫六」なる者が芸事に優れ、田楽、田舞などを土地の豪族を介して里人に踊らせたものが始まりと言われ、時代のを経て現代に至っている。平成7年発掘された山屋経塚から出土した二つの壺には「常滑三筋文壺」(岩手県立博物館蔵)等があり、これによって山屋地区と平泉・藤原氏との関連も裏付けられた。 毎年1月15日前後の休日にその一部を山屋公民館において踊り始め公演として実施している。昭和56年「国・重要無形民俗文化財」となる。 (山屋田植保存会より) 「きれいな あねさん(若い女性)、つれできた~」 と言われて登場した四人の女性。 しかし、手ぬぐいをとってみると、みんな男の子です!! 足の使い方などが、とてもしなやかで驚いてしまいました…。 小学生から大人までが、この伝統芸能に携わり、 大切に受け継がれていることが、演技から見ることが出来ました★ 二つ目の団体は、花巻農業高校鹿踊部による「春日流鹿踊り」です♪ 本校は明治39年の創立で108年を迎えた歴史と伝統ある学校です。童話「銀河鉄道の夜」の作者である宮澤賢治が4年4ヶ月本校で教鞭を執ったことでも知られています。 鹿踊り部は、昭和33年、花巻市東和町の春日流鹿踊保存会のご指導を仰ぎ始まり、今年で56年を迎えました。現在部員は3年生5名、2年生6名、1年生9名の計20人で、地元の福祉施設でのボランティア公演や各種イベントでの公演をはじめ、東京などへの県外公演を含め、年間約30回の公演を行っています。また昨年は長崎県で行われた全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門に出場し、岩手の郷土芸能「鹿踊」を全国にアピールすることができました。(花巻農業高校鹿踊部より) 鹿踊りの見どころのひとつは、はやり衣装ですね! 大きな鹿のかぶり物に、ながーーーーーーーーーい角!!! 見るからにに重そう……(> <;) それにもかかわらず、 頭を前後に振ったり、ジャンプ(上の写真の中央の鹿の注目!)したり、 若い鹿たちを躍動的に表現しており、すばらしい演技でした!! ☆おまけ☆ ↑鹿踊部のTシャツが素敵ですね!サポートお疲れ様です! レポート~芝生広場編~に続く 2014.9.14sakuyama
広重と胡堂の作品、両方を楽しめる企画展!第三期スタート!!
6月から始まった企画展 歌川広重「東海道五十三次」・野村胡堂『三万両五十三次』は、 広重の版画と胡堂の小説を、一緒に味わえる企画展です! 9月5日(金)から第三期がスタートし、10月19日(日)で企画展の全てが終了になります。 東海道五十三次とは、 浮世絵師・歌川広重が描いた、東海道五十三次の宿場町や景色の風景版画です。 江戸の日本橋から、京都の三条大橋まで続く東海道にある、 53箇所の宿場町や風景を描いたものです。 江戸の「日本橋」を出発し、「箱根」の関、「大井川」の徒歩渡り、「宮」の渡し… そして、東海道の中でも難所といわれる鈴鹿の関を越えると、目指す「京」は目の前! 第三期では、赤坂~京までの20点を展示しています。 ※写真では明るく見えますが、会場は作品保護のため、照明を落としております。 ご理解と、ご協力をお願いします。 小説『三万両五十三次』とは、 歌川広重の東海道五十三次に影響を受けて、胡堂が執筆した長編小説です。 もちろん舞台は東海道五十三次! 江戸の日本橋を出発し、53ヵ所の宿場町を越え、京都の三条大橋へ向かいます。 物語は、馬場蔵人が京都まで送り届けるはずの三万両をめぐり、 盗賊たち、攘夷派の武士たちが大奮闘! しかし、重要人物である“真琴”の死をもって、物語は急展開します。 (あらすじは、過去のブログ、または記念館でご覧ください♪) 野村胡堂の代表作といえば『銭形平次捕物控』ですが、 この『三万両五十三次』も、かなりの名作ですよ(^-^)! 展示では、小さなキャラクターたちも、物語をちょこっとナビゲートしています♪ 展示室は、受付を過ぎて右奥の、こちらの広重ロード(廊下)を進んだ先です。 (ちなみに、廊下から企画展関連の展示をしていますので、こちらもぜひ!) みなさまのご来場、お待ちしております!! 2014.9.6sakuyama
こども映画会の前に、ミニコンサート♪♪♪
今日から開催している、 夏休みこども映画上映会(NPO法人野村胡堂・あらえびす記念館協力会主催)に合わせて、 アコーディオンと歌による、ミニコンサート(テコ&コロ主催)がギャラリーで行われています。 初日の今日は、約30人のこどもたちが歌の時間を楽しみ、 その後は、涼しいホールでゆったりと映画を観ました♪ 手作りのボードと、可愛らしい振付がこどもたちに人気の様子★ ミニコンサートは10時10分頃から15分間、映画上映会前に行われます。 ※8/7(木)はミニコンサートがお休みです。映画上映会は開催します。 夏休みこども映画上映会の詳しい内容は、イベント・講座のページをご覧ください(^^)♪ 2014.8.5 sakuyama
開館20周年事業 企画展第二期が始まりました
6月から開催している企画展 歌川広重「東海道五十三次」・野村胡堂『三万両五十三次』 胡堂の小説に合わせて広重の「東海道五十三次」を3期に分けて全て展示します。 7月23日(水)からは第二期に入り、展示している作品を入れ替えました。 広重の東海道五十三次は、由井(ゆい)~御油(ごゆ)までを展示しています。 胡堂の小説の中では、いろいろな展開がありながら東海道を半分過ぎたところ。 三万両をめぐり、攘夷派の武士たち、盗賊たち、主人公馬場蔵人の間では、 まだまだ波乱が巻き起りそうです…。 第一期を見逃した~~~~という方へ! 第一期で紹介した胡堂の作品は、 東海道五十三次の保永堂版(複製)と合わせてギャラリーに展示しています。 8月31日(日)まで展示しますので、夏休みは涼しい記念館へお越し下さい(^^)♪ 2014.7.27sakuyama
あらえびす記念館バスツアー★レポート
まだまだ、じぇじぇじぇで 久慈さ行ってきました~!!! 7月14日(月)、昨年NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」で超話題になった、 北三陸市!・・・・・・ではなく、久慈市に行ってきました(^0^) まずは、北限の海女さんたちによる素潜り!! 海女さんたちがとってきたウニを、その場でいただくことができ大満足でした♪ お昼は久慈グランドホテルにて。 しっかり「まめぶ汁」をいただきましたよ~! ドラマの中であきちゃんも言っていましたが、 確かに、甘いんだかしょっぱいんだかどっちなんだか… でも、私は好きな味です…また食べたいです!(笑) お昼休憩の間に、久慈駅周辺を散策しました♪ ドラマのロケ地やモデルになったビルと、 「あまちゃんハウス」もちょこっと見学できました! その後は、「やませ土風館」で休憩&お買いもの♪ 地元の食材やお土産品など、たくさん買いました(^^) 最後は、久慈の琥珀博物館を見学しました。 内陸の私たちにはちょっと馴染みがない「琥珀」ですが、 ガイドさんがついて説明してくださったので、興味深く見学することができました! 久慈の琥珀は、恐竜時代にもあたる約8,500万年前の樹脂の化石だそうです(*0*;))))))) テレビドラマのロケ地から、ご当地グルメをいただき、有名博物館も見学し、 お楽しみ盛りだくさんのバスツアーでした! さて、次回のあらえびす記念館バスツアーは、 10月27日(月)秋田県仙北市 角館 を旅します~♪ ちょうど紅葉も綺麗な季節ですね~!ご参加お待ちしています! ※詳しくはホームページのイベント情報や、直接記念館にお問合せください。 ★おまけ★ ちょっと写りが悪いのですが・・・ ヒロインアキちゃんが走っていく灯台 ♪星よりひそかに~~~雨よりやさしく~~~…と、 海女クラブのおばちゃん達が歩く坂。 左に行くと「ストーブさん」がいた監視小屋があるそうです。 (ドラマを見ていないと分からない写真かもしれません!すみません!) … 続きを読む
スオノ・ディ・モリオカ コンサート★レポート
(レポートがだいぶ遅れてしまいましたが・・・(+_+;)) 7月6日(日)に、ピアノコンチェルト&ストリングカルテット スオノ・ディ・モリオカ コンサート(NPO法人記念館協力会主催)が 無事に終了しました!!! 当日はお天気にも恵まれ、80人を超えるお客様がご来場くださいました! どうもありがとうございました~(^^)♪ 楽器やモーツァルトのエピソードをたくさんお話してくださり、 「うんうん・・・」と、うなづいて聴いている方も多かったですね。 最後に演奏したピアノ協奏曲(ピアノと弦楽四重奏による演奏)は、 迫力はもちろんのこと、メンバーの息がぴったりで、 ピアノとヴァイオリンが対話をしているよう場面は、とっても素敵でした☆ スオノ・ディ・モリオカのみなさんは、秋に第3回定期演奏会を開催するそうです。 今回は第1楽章のみの演奏だった、ベートーヴェンのラズモフスキー第3番も、 定期演奏会では全曲演奏するそうです。 興味のある方は、ぜひご来場ください♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2014年11月9日(日)18:30~開演予定 会場:盛岡市民文化ホール(マリオス)小ホール ショパン:スケルツォ 第4番 ホ長調 ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第9番「ラズモフスキー第3番」 ブラームス:ピアノ四重奏曲第1番ト短調 ※詳しくは スオノ・ディ・モリオカ ホームページをご覧下さい♪ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ スオノ・ディ・モリオカのみなさん、素敵な演奏をありがとうございました! 左から、代表の片桐薫さん、資歩さんご夫妻、 解説をしてくださったピアノストの三神樹美さん、 笑顔が魅力的なヴィオラの藤澤英子さん、 素敵な音色を響かせてくださったチェロの石原博史さん。 2014.7.27 sakuyama
復活そして誕生
没後50年を経て、野村胡堂・あらえびすの名作、そして初の読本となる『野村胡堂・あらえびす-「銭形平次」と「音楽評論」を生んだ岩手の文士』が発売されております。当館またはお近くの書店でお買い求めください。 野村胡堂・あらえびす 初公開となる岩手への里帰りの日記や人気作家による書下ろしエッセイ、貴重な写真を多数掲載した、全方位から野村胡堂・あらえびすを紹介する初の読本。 発売:株式会社文藝春秋 定価:1,380円+税 銭形平次捕物控傑作選(全3巻) この本を読まずに、捕物小説は語れない!全383篇のなかから選りすぐりの傑作を全3巻に。各巻末には、詳細な江戸用語解説が付されており、とても読みやすくなっております。 発売:株式会社文藝春秋 定価:各巻490円+税 音樂は愉し 流行作家として「銭形平次」シリーズをヒットさせ、批評家としてわが国新聞紙上初のSPレコード評も執筆。SPレコード蒐集に精魂を傾けた野村あらえびすによる名随筆が復刻。 発売:音楽之友社 定価:2,000円+税
野村胡堂の『三万両五十三次』って、どんな物語?
6月も、あっという間に終りですね! 今月は企画展が始まり、開館20周年の記念式典がありと、盛りだくさんの一ヶ月でした!(^O^) そして昨日は、IBC684ラジオカーが記念館にやってきました★ 6月10日(火)~開催している企画展を取材していただきました。 なんとも赤がまぶしい!!! 放送内でも、胡堂の浮世絵へかける情熱や、作品創作の苦労などを紹介しましたが、 野村胡堂の『三万両五十三次』っていったいどんな話??? …という方が多いと思いますので、 今日は、物語の「あらすじ」を簡単にご紹介します! 時は安政5年の幕末、黒船が来航し、日本が開国した直後の物語です。 主人公の馬場蔵人は、江戸幕府の命令で京都の天皇のもとに、赴くことになりました。 アメリカとの、ある条約を結ぶ許可を得るために、 どうしても必要だった三万両という大金を、京都に運ぶ大役を任されたのです。 条約の締結に反対する攘夷派の武士たち、そして、大金を狙う盗賊たちが、 馬場蔵人を追いかけながら東海道を上っていく、波瀾万丈な旅物語です! ある条約とは、実際にアメリカと結ばれた「日米通商修好条約」のこと。 主人公の馬場に命令した、江戸幕府の老中堀田備中守という人物も、実在しています。 どこからが作り話なんだろう?と思うほど、史実に基づいた物語になっているのです。 どうですか!?おもしろそうでしょう!? 自信を持って言いますが、、、この作品、おもしろいです!!! では、なぜ「三万両」が必要だったのか…? どうやって東海道を上っていったのか…? その秘密は、また今度お話しましょう!(^皿^*) 展示は、広重の浮世絵版画『東海道五十三次』と照らし合わせて紹介していますので、 胡堂の作品の風景を、よりイメージしながら楽しめると思います★ パネル展示だけでなく、実際に作品も読めますよ♪ IBC684ブログでも、企画展を紹介していただきましたので、こちらもご覧下さい! … 続きを読む
企画展 開催中!
6月10日(火)から、開館二十周年事業企画展、 歌川広重「東海道五十三次」 ・ 野村胡堂『三万両五十三次』 がスタートしました! 今回は、広重の風景画に大きな影響をうけて、 胡堂が執筆した長編大作『三万両五十三次』を紹介しています。 影響を受けただけではなく、 胡堂は、広重の風景画「東海道五十三次」を一枚一枚集めるほど熱中しました。 江戸文化に深い関心があった胡堂は、すっかり広重ファンになったようです(笑) 企画展初日は、FM岩手の紫波こびるFMさんの生中継! 写真は、紫波こびるFMのリポーター畠山泉さん♪ 畠山さんは演劇が得意ということで、 胡堂の『三万両五十三次』の会話のワンシーンを、畠山さんと私(作山)とで演じてみました。 とーーーーーーーっても緊張しましたが、畠山さんご指導のもと、 楽しんで演じさせていただきました♪ お聞きくださったみなさん、ありがとうございました!! (ちなみに、紫波こびるFMは、 毎週火曜日午後3時~放送!紫波町の話題たっぷりです!どうぞお聞きください♪) 会場は、このような雰囲気です。 写真には明るく映っていますが、作品保護のため、会場内は薄暗くなっております。 メインの展示会場までの長い道中(「東海道五十三次」だけに…笑)には、 広重との馴れ初めや、風景画にどれだけ熱中していたか、 作品の題材を決めるまでのいきさつ、創作にかけた苦労、自分が描いていた絵の話など、 アツく語っている胡堂の言葉を並べました。 ここも企画展の一部ですので、ぜひご覧下さい! 胡堂作品は「銭形平次」だけじゃない! 熱中して集めたものはSPレコードだけじゃない! 開館20年の節目に、みなさんが、まだ読んだことのない胡堂作品と、 広重の風景画にも熱中していた胡堂の一面に、出会っていただければ嬉しく思います。 企画展は三期に分けて開催しますので、詳しくはイベント情報をごらんください。 ご来館お待ちしています!
今年も咲きました!
4月14日は野村胡堂の命日です。 当時としては長生きで、昭和38年に80歳で亡くなりました。 いつもこの時期になると、記念館にカタクリの花が咲くのです(^^)* 「野村胡堂」と「カタクリの花」はどんな関係が…?? 胡堂は大学進学のために上京してから、 生涯のほとんどを東京で過ごしましたが、 ふるさと紫波町を懐かしみ、後年に、このようなうたを詠みました。 「故郷の 春日の丘に かたくりの むれ咲くころの なつかしきかな」 胡堂が思い出すふるさとの風景のひとつは、 暖かな春の日差しを浴びて、丘一面に咲くかたくりの花…だったのです。 紫波町の城山公園には、このうたの歌碑があります。 もうすぐ城山公園の桜も、咲き始める頃でしょう。 お花見に行かれた際は、ぜひこの歌碑をみつけてくださいね。
ギャラリーで写真展を開催中!
現在、ギャラリーでは、紫波天文同好会による写真展「彗星~紫波・矢巾から撮影~」を開催しています。 「彗星」と言われてすぐに浮かんでくるイメージは、明るく光る、ながーい尾! その長い尾が「ほうき」に似ていることから「ほうき星」とも呼ばれていますね♪ なかなか見る事が出来ない彗星ですが、 これは明るくなる予測が難しいため、私たちの知らないまま静かに去ってしまっているのです。 (写真の写りが悪くてすみません…) 「彗星」の主な成分は「水」で、例えると直径約10キロメートルの大きな雪だるま!! 地球のように太陽を回る天体で、何十年、何百年という周期で回る彗星もあれば、 二度と太陽に近づくことのない彗星もあります。 そして太陽に近づいた時、尾をひく彗星になり、私たちが地球から見ているわけなのです! この写真展では、主に紫波町と矢巾町で撮影された彗星の写真20点が展示されています。 最近の写真では、2013年11月に撮影された写真もありますよ! 写真展は3月9日(日)まで!どうぞご覧ください! ※写真展のみをご覧になる方は、受付にお申し出ください。 また、ギャラリー展をお考えの方は、記念館までお問合せください。 2014.2.20 sakuyama
『音樂は愉し』 黎明期音盤収集家随想 出版のお知らせ
この世にうまれて、芸術を味わう喜びは、何に譬(たと)うべきであろう。 文芸、美術、音楽、演劇それぞれの分野から、 掬(く)みとれるだけの高いもの、美しいものを掬みとって、 自分の生命を豊かにする望みがなかったならば、 何とこの世の味きなく淋しいことであろう --本書「レコードの聴き方」より-- 昭和21年に出版された野村あらえびす著『音樂は愉し』が、復刻版として音楽之友社から出版されました。(☆当館でも資料協力いたしました。) お近くの書店または音楽之友社からお求めください。 (音楽の友社web)
秋の空~♪
今日の午後4時45分頃の夕焼けです~(*^^) 秋の空って、夕焼けの色もきれいですが、流れる雲もすてきですよね~~~♪ ↓もうひとつの夕焼け!窓に映っているのが分かりますか?? これは、記念館に来なければ見られない夕日ですよ★ みなさんにも一度見ていただきたい!!! (記念館から眺める夕焼け写真コンテストなんてどうでしょう…うふふ(^^)?)
芸術の秋!
現在ギャラリーでは、堀内幸一さんの絵画展「鈍行画廊」(主催:堀内幸一氏)を開催しています!! 80号や100号といった大きなキャンバスに、 鉱山の跡地や、遠くまで続く道と海、雪深い山間の様子などが描かれています。 堀内さんは90歳を目前に控え、「画文集の出版」を目標に 野村胡堂・あらえびす記念館協力会が主催する文章講座・エッセイコースを受講されました。 そして今年、画文集が完成し、出版しました! 「絵」と「文」でご自身の想いを表現したすばらしい作品です(^^)! 土・日曜日は記念館へいらっしゃるので、ぜひ直接お話をうかがってみてください! 堀内さん、いつまでもお元気で「絵」と「文」の作品づくりを続けてくださいね★ 絵画展は11月30日(土)まで! ※絵画展のみをご覧になる方は、受付でお申し出ください。また、ギャラリー展をお考えの方は、記念館までお問合せください。
焼き芋をいただきました!
今日の昼前、お隣の岩手保育学園の園児のみなさんが、 ホカホカの“焼き芋”を届けてくれました!! 午前中は焼き芋会だったそうで、記念館職員にもおすそわけとのこと★ 大きな焼き芋は、お昼においしくいただきました(^^)! ごちそうさまでした~*
キッズフェスティバル★レポートその3
キッズフェスティバルのレポートその3は、 今年初めて開催した夜の部の様子をご紹介します! 夜の体験コース一つめは、 星や月を観察したり、夏や秋に見える星座のお話を聞くコース☆ ギャラリーに木星出現!(笑) 写真は木星設置中で、しかも少し見難いのですが、 この木星は、模様までじっくり見れるんですよ! そして外では、こちら(↓)の大きい望遠鏡で月を見ました! 肉眼で見るとぼやぁ~んとしていた月も、望遠鏡で覗くとクレーターまではっきり見えるんです! ハイビジョンのテレビ番組でしか見たことのない月を、 自分の目で見ているというのは、かなり感動でした…\(;O;)/ 夏の大三角形は、今ちょうど真上に見えるらしいですよ! 目印は、大きな十字架!見つけてみて下さいね☆ 夜のコース二つ目は、 ライトトラップを使い、光に集まる夜の虫たちを観察するコース☆ 集合時間になると、虫取り網と虫カゴ持参して、張り切っている子供達もちらほら! 虫が集まるまでは、まわりの木々を観察したりして、 彦部の豊かな自然もたっぷり楽しみました! 虫を見つけては、 「こんなのつかまえたよ!」 「これなあに?」 「どうじてこうなってるの?」などなど・・・、先生方は大忙し!(笑) たくさんのキレイな羽根の虫たちを見つけたり、虫に優しく触れてみたり、 親子で虫に親しめる楽しい観察会になりました!! 3つに分けてご紹介しましたが、 今年のキッズフェスティバルも大盛況のうちに終わることができました。 ご協力くださいました各団体、講師の皆様、 ご来場くださいました多くのみなさま、どうもありがとうございました!\(^O^)/
キッズフェスティバル★レポートその2
キッズフェスティバルのレポートその2は、 昼の部の様々な体験コーナーの様子をご紹介します! まずは館内の体験コーナー♪ ≪お琴≫ 爪をつけて、「さくら」の演奏に挑戦しました。音が響く仕組みも丁寧に教えてもらいました! ≪尺八≫ 音を出すのは結構難しいのですが、楽器の原理は小学校で習うリコーダー似ているんです! 竹の質感で、少し曲がっているのもまた良いですね♪ ≪お煎茶≫ 実は野村胡堂も、お茶がとっても好きでした! 先生に入れてもらった本物の「お茶」の味、ちょっとだけ苦く感じたかな(^^)? ここからは芝生広場で行った昔遊びのコーナーです! ≪水でっぽう≫ 野村館長手作りの水でっぽう! 服がびしょびしょでも「遠くまでとばしたよ~!!」と、みんな大はしゃぎでした! ≪竹馬≫ つま先に力を入れて、歩きながらバランスを取るのがポイント! スタッフに支えてもらいながら一生懸命挑戦していました! ≪弓矢≫ こちらも野村館長の手作り!昨年から大変好評なんですよ~(*^^)b ≪わなげ&フラフープ≫ わなげは、小さな子供からシニアのスポーツとしても親しまれている遊びです。 子供達はどれだけ遠くから投げられるか、自分の限界に挑戦していました! フラフープは腰で回すのはもちろん、腕で回したり、首で回したり、縄跳びのようにして遊んだり! 小学校のときに、体育館でよく遊んだなー…なんて思い出してしまいました(^・^) ≪めんこ≫ めんこの絵も手作りです!成功させるには、紙の厚さと大きさと勢いがポイントのようです! ≪餅つき≫ 午後15時頃から紫波町のもち米を使った餅つきがスタート! お餅のふるまいも行われました。柔らかくてとてもおいしかったです(o^-^o) この日はちょうど地元大巻の秋まつりで、イベント中に大巻山車が到着しました! … 続きを読む
キッズフェスティバル★レポートその1
9月14日(土)は「キッズフェスティバル in あらえびす2013」を開催しました! およそ350人の方が来場し、特にステージ発表はとても盛り上がりました(^^) レポートその1では、ステージ発表の様子を紹介します!! まず、13時30分から始まったのは大槌町の「吉里吉里虎舞講中」 大槌町と紫波町は約30年前から交流を続けており、 今回はそのようなご縁もあって出演をお願いしました。 この虎舞には「大漁祈願」「海上安全祈願」の願いが込められているそうです。 なかなか見る事ができない大槌町の虎舞。 私は今回初めて見させて頂いたのですが、、、 躍動感あふれる舞に圧倒されましたし、 子供達の大人に負けない堂々とした姿に感動しました\(;O;)/ 本当に素晴らしかったです!!! 続いて14時10分からは、雫石高校郷土芸能委員会による「上駒木野参差踊り」と「よしゃれ」 雫石高校郷土芸能委員会は平成7年に「よしゃれ研究会」として創設され、 地域の祭りや各種イベントに出演しています。 全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門でも岩手県代表として何度も出場し、 優秀賞を受賞しています。 赤い蓮の花笠が同じ方向を向いてぴったり揃い、 七色の腰帯がひらひらとゆれ、とても華やかな踊りでした。 そしてなにより、高校生のみなさんの笑顔がいい!! この日は、午前中にも別のイベントの出演があったそうですが、 疲れた表情ひとつ見せず、最後まで元気に踊り切ってくれました。 地元の若者によって郷土芸能が伝承されていくことは、とても素晴らしいことですね☆ 大槌町の吉里吉里虎舞講中のみなさん、雫石高校郷土芸能委員会のみなさん、 本当にありがとうございました!! 昼の部(レポートその2)へ続く…☆